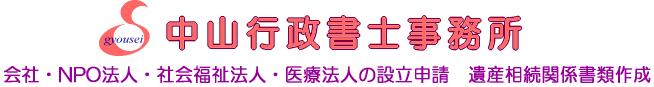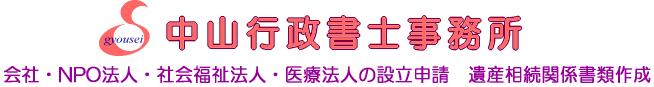|
もし、負債超過とわかったら!
限定承認・・・・相続人全員の同意が必要
相続放棄・・・・1人でもできます自己のための相続開始を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。 |
期限を過ぎると、一切の資産と負債を引き継ぐことになります。
相続豆知識:相続税の基礎控除
5000万円+(1000万円×相続人の数)
:相続放棄した人は民法上は、はじめから相続人ではなかったことになるが相続人の数には含めます。
:生命保険や損害保険のうち 500万円×相続人の数 が非課税
:死亡退職金のうち 500万円×相続人の数 が非課税 |
4ヶ月以内(準確定申告)
故人に事業収入や不動産収入があり、年の途中で死亡した場合は、相続人は、相続開始後4ヶ月以内に申告することが決められています。
10ヶ月以内(相続財産の確定・評価)
(特別代理人の選任)・・・ 相続人に未成年者がいるとき
親族などの中から適切な人を候補者に立て、子供の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。未成年者の子が2人いれば2人の特別代理人が必要です。
(遺産分割協議書の作成)
遺産分割協議書の作成は、専門家の行政書士に依頼しましょう。
協議の成立には、全員の合意が必要です。遺産分割協議の話し合いがうまくいかない時は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申し立てを行います。調停が不調の時は、審判に移されます。合意ができると、協議書の作成に入ります。
誰がどの財産を相続したか、財産の特定(不動産なら登記簿どおりに地番や面積を記載)をすること。相続人の氏名・住所は、住民票どおり記載のこと。全員の署名、捺印と印鑑証明書が必要です。
不動産・自動車・ゴルフ会員権の名義変更や銀行・郵便局の預貯金の引き出しにも、遺産分割協議書は必要です。印鑑証明書とセットで数部用意しておきましょう。
(不動産の移転登記、財産の名義変更)
(相続税の申告・納付) |